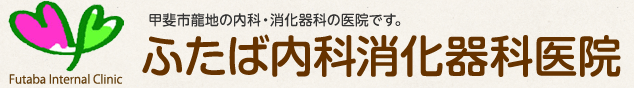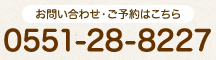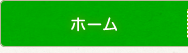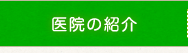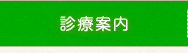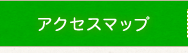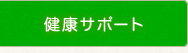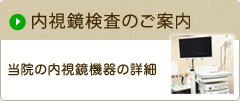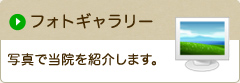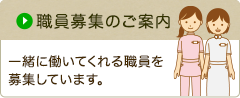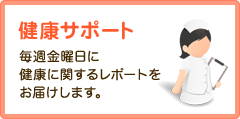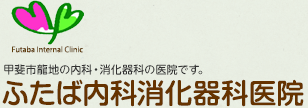病気と治療の基礎知識
白内障

眼の中でカメラのレンズに相当する水晶体が濁って光が通りにくくなり、視力が低下する病気が白内障です。高齢になると発症する加齢性白内障のほか、生まれつきの先天性白内障や、糖尿病など他の病気に伴って起こる白内障などがあります。ここでは、患者さんの数が多い加齢性白内障について説明します。
日本人を対象に行われた調査研究の結果、水晶体がわずかに濁る初期の白内障を含めると、60歳代の高齢者では6割から8割、70歳代では9割前後に白内障があることが明らかになっています。濁りの度合いが少なければ様子を見ることもありますが、視力が低下して日常生活に不自由を感じる場合には、手術が検討されます。
現在、広く行われている白内障の手術では、まず眼球に小さな穴を開け、濁った水晶体を超音波で砕いて吸引します。その上で、この穴から人工眼内レンズを挿入します。局所麻酔で済み、日帰り手術が可能です。治療技術の進歩により、90歳を超える人でも安全に手術を受けられるようになっています。
最近では、多焦点眼内レンズやレーザー装置を用いた手術も普及しています。従来の眼内レンズは単焦点で特定の距離しかピントが合わず、いくつも眼鏡を付け替える必要がありました。これに対し、多焦点眼内レンズを装着すると、近くや遠くにピントを合わせることができるようになります。レーザーを用いた手術では、より正確に眼内レンズの固定ができるほか、超音波照射時間を減らすことができ、手術後の回復が早くなるとされています。
高齢になってからの生活の質を保つためには、40歳を過ぎから眼科で白内障をはじめとする定期的な検査を受け、必要に応じて治療やケアを受けることが望ましいでしょう。